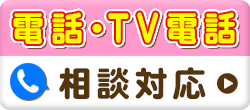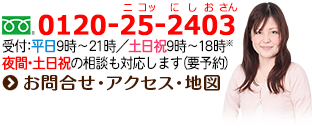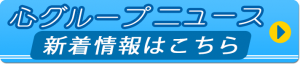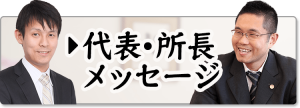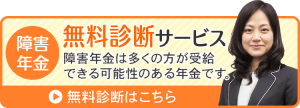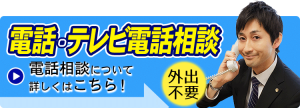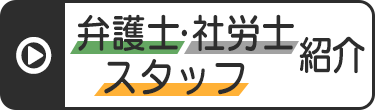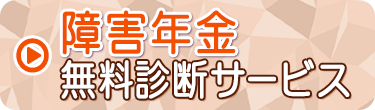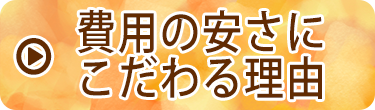くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
1 くも膜下出血とは
脳の外側には3つの膜があり、外側から「硬膜」「くも膜」「軟膜」といいます。
くも膜下出血とは、これらのうちのくも膜と脳の空間に存在する血管が切れて起こる出血のことです。
くも膜下出血による後遺障害は、出血した部位や出血量、発症後から治療に至るまでの期間、合併症の有無などに応じて様々なものがあります。
運動障害が残ったり、食べ物や水を上手に飲み込むことができない、視野が狭くなるなどの局所症状が生じたり、言語の障害、排せつの障害、高次脳機能障害が生じることもあります。
そのため、くも膜下出血で障害年金を請求する場合には、症状に合わせた診断書を作成してもらうことがポイントになります。
2 運動障害
いわゆる半身まひの場合には、肢体の障害用の診断書を作成してもらうことになります。
くも膜下出血を含む脳血管障害により、肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる場合には、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定するとされています。
そのため、以下のような日常の動作ができるかどうかが重視されます。
ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ 下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
3 その他の障害
そしゃく・嚥下の障害、視野(眼)の障害、言語機能の障害、高次脳機能障害等の精神の障害、排せつの障害についても、それぞれの障害に応じて作成な必要な診断書があるので、症状にあわせて診断書を作成してもらい、提出する必要があります。
4 障害の併合
ただ、単純にくも膜下出血によって生じた障害すべてについて、診断書を書いてもらえればよいというわけでもありません。
診断書を作成してもらうのにも費用が掛かりますし、3級の障害が複数あっても2級に等級が上がる場合もあれば、3級のままの場合もあります。
そのため、各障害がどの等級に該当する可能性があり、それが併合した場合に等級が上がるかどうかを考え、必要かつ十分な診断書の作成を依頼することが、くも膜下出血によって障害年金を申請する場合のポイントといえます。